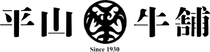なぜ但馬牛は美味しいのか?── 科学とデータで紐解く「美味しさの秘密」|アンバサダー講習会レポート①
「但馬牛って、なんであんなに美味しいの?」
精肉店に勤めていると、よく耳にするこの質問。
確かに“美味しい”と言われることは多いけれど、実はその理由をきちんと説明できる人は少ないかもしれません。
この記事では、但馬牛アンバサダー育成講習会で学んだ「但馬牛の美味しさの秘密」について、研究結果や科学的根拠とともに分かりやすくご紹介します。
但馬牛アンバサダー育成講習会第1回 講義名「但馬牛の味の特徴」
講師:県立但馬牧場公園但馬牛博物館副館長 野田昌伸先生
1. そもそも「美味しい牛肉」とは何?
1-1. 食べ物の「美味しさ」を決める要因とは

(県立農林水産技術総合センター畜産技術センター所長 岩本英治様の講義資料より)
「食べ物の美味しさを決める要因」についてまとめられた上記の図を見ていただくとわかるように、人は食事をする際、以下のような五感や環境的要因によって「美味しい」と感じています。
- 味覚(甘味・酸味・塩味・苦味・旨味+辛味・渋味)
- 嗅覚(香りや風味)
- 触覚(やわらかさ、歯ごたえ)
- 視覚(色・光沢)
- 聴覚(咀嚼音)
- 外部環境(雰囲気、温度)や、その人自身の体調や気分も影響します。
この中でも、特に「嗅覚=香り」は美味しさに大きな影響を与えると言われています。
実は「味」は、舌だけで感じるものではありません。
食べ物の香りが鼻を通って脳に届くことで、初めて「美味しい」と感じるのです。
風邪をひいて鼻が詰まったときに、何を食べても味がしない…と感じた経験はありませんか?
それは、嗅覚が働いていないから。
それほどまでに「香り」は、味の認識に大きく関わっているのです。
1-2. 牛肉の美味しさを決める3つの要素
次に牛肉の美味しさについてですが、上記の五感の中でも特に以下の3つが大きなカギになります。
-
嗅覚(風味・香り):モノ不飽和脂肪酸(MUFA)が決め手
牛肉の香りに大きく影響するのが「モノ不飽和脂肪酸(MUFA)」という成分。 この「モノ不飽和脂肪酸(MUFA)」の含有量が一定以上高いと、肉の香りが豊かになるといわれています。 -
触覚(やわらかさ):脂肪の質が重要
口に入れた瞬間にとろける柔らかさも、和牛の大きな魅力です。 これは、脂肪のキメの細かさ(いわゆる「小ザシ」)や脂肪交雑のバランスが関係しています。 ただし脂肪が多すぎるとくどくなるため、適度なバランスが重要です。 -
味覚(旨味):アミノ酸と脂肪の味わい
牛肉の旨味はアミノ酸のバランスと脂肪の質に関係しています。 “甘味”“旨味”を感じやすい脂肪は、美味しさを底上げしてくれます。
2. 臨床データで見る但馬牛の美味しさ
2-1. 但馬牛と他県産牛の食味試験
「本当に但馬牛は他の牛より美味しいの?」
そんな疑問に答えるために、実際に行われた食味試験があります。

(県立農林水産技術総合センター畜産技術センター所長 岩本英治様の講義資料より)
◆ 但馬牛と他県産牛を用いた食味試験
平成22年、但馬牛と他県産の黒毛和牛43頭を用い、サーロインの食味比較試験が行われました。
判定を行ったのは、味覚に優れた「五味識別テスト」の合格者たち(合格率39%、なかなかの難関テストです)。
もちろん、どちらが但馬牛かは伏せた状態で評価をします。

(県立農林水産技術総合センター畜産技術センター所長 岩本英治様の講義資料より)
結果は、但馬牛の方が他県産牛に比べて
- 風味
- うま味
- やわらかさ
- 総合評価
の項目で高評価。特に、風味・うま味・総合評価については、有意に優れているという評価でした。
客観的なデータとして「但馬牛は美味しい」と実証されたのです。
2-2. 香気分析による裏付け
さらに、アサヒビールの香り研究員による「香気分析」でも、但馬牛は他県産牛より”和牛香”が強いということが明らかになりました。
甘く、ココナッツのような香りが混ざった独特の風味。生肉ではなく、加熱することで強く感じられます。特にすき焼きやしゃぶしゃぶといった低温調理で際立つ香りです。「すき焼きはお肉の良し悪しが最もわかる食べ物」と言われる理由はここにあるのですね。この和牛香がより強いということも、但馬牛の美味しさに寄与しています。
では、なぜ但馬牛は美味しいのか?美味しさを裏付ける科学的根拠はあるのか?次はそちらについて、具体的に説明していきます。
3. 但馬牛が美味しい理由とは
3-1. モノ不飽和脂肪酸(MUFA)について
モノ不飽和脂肪酸(MUFA)は、香り・風味・旨味のすべてに関係する脂肪酸。このモノ不飽和脂肪酸(MUFA)が多いほど、牛肉は「香り豊かで美味しい」とされます。

(県立農林水産技術総合センター畜産技術センター所長 岩本英治様の講義資料より)
2016年~2017年1月までに測定された8,366頭分の研究データによると、但馬牛は他県産牛と比べて優位にモノ不飽和脂肪酸(MUFA)の含有量が多いということがわかりました。
このように、但馬牛の美味しさには、科学的根拠があるのです。
さらに、モノ不飽和脂肪酸(MUFA)の含有量は遺伝的に受け継がれる性質であることも判明しています。
つまり、優れた血統を守り続けることで、脂の質=美味しさを維持することや、さらなる品種改良を行うことが可能なのです。では次に、但馬牛が「遺伝(血統)をどう受け継いでいっているのか」という部分をご紹介します。
3-2. 但馬牛の肉質と「閉鎖育種」について
但馬牛には、遺伝的な特質とその飼育環境から、「小ザシ」と呼ばれるサシ(霜降り)が入りやすいという特徴があります。この「小ザシ」は融点が低く、人肌で溶けます。
また、但馬牛は遺伝的にしなやかな筋肉によって適度な脂肪を留めることができ、それが美しくきめの細やかなサシとなります。また、上品な甘みのある赤身が特徴で、脂の風味が良いです。
そんな特徴を持つ但馬牛は、「閉鎖育種」という特殊な方法で育てられています。これは、兵庫県内で但馬牛同士のみを交配させ、他県の血を一切入れないという管理体制のことです。この厳格な交配管理により、優れた肉質の遺伝子が代々受け継がれています。
このような管理体制を導入しているのは、全国数多のブランド牛の中でも但馬牛だけです。なかでも但馬牛発祥の地である美方郡は、兵庫県の中でもさらに美方郡内のみで閉鎖育種をすることで純血を守り、その肉質は高く評価されています。
3-3. 徹底した流通管理システムと美味しさの改良
但馬牛が他県産牛と違う部分としてもう一点挙げられるのが、厳格な流通管理システムです。国産牛肉は、食の安全・安心を確保するための取組みの一つである「牛トレーサビリティ制度」によって、すべての個体が登録・管理され、出生から出荷までの履歴がトレースできる仕組みとなっていますが、但馬牛の管理にはさらに独自の「但馬牛血統証明システム」が導入されています。
また、但馬牛の種雄牛(お父さん牛)はすべて県の管理下にあります。そのため、兵庫県外の但馬牛以外との交配は不可能であり、閉鎖育種をより確固たるものにしています。この管理体制によって、但馬牛の品質は支えられているのです。
さらに、但馬牛の改良や研究を行うために、兵庫県の北部農業技術センターには畜産部が設置されており、日々研究員が但馬牛の美味しさの改良に向き合っておられます。
3-4. 生産者の高度な飼育技術
但馬牛を育てる農家の方々の飼育技術の向上も、但馬牛の美味しさを引き出す大きな要因のひとつです。
但馬牛に認定されたもののうち、さらに厳しい条件をクリアした牛肉のみ神戸牛に認定されますが、但馬牛の神戸牛認定率は年々上昇しています。
平成21年には50.7%だったのが、令和3年にはなんと92.2%もの認定率となっています。つまり、但馬牛の92.2%は神戸牛なのです。
美味しい牛肉になるためのより厳しい条件を満たすことが可能となっているのは、県が開発した「但馬牛肥育マニュアル」の定着も理由のひとつですが、なにより農家の方々の牛への愛情とたゆまぬ努力があってこそ。農家の方々の飼育技術の高さも、但馬牛が美味しい大きな理由のひとつです。
まとめ
但馬牛の美味しさには、科学的にも証明されている肉質の良さ、閉鎖育種による純血の継承と美味しさの改良、厳格な流通管理システム、そして生産者による高い飼育技術によって守られています。
神戸ビーフの素牛(もとうし)としても知られる但馬牛は、「和牛の源流」として唯一無二の存在です。
食べた瞬間に「他とは違う」と感じるのは、そんな背景があるからなのです。
ぜひ一度、実際に食べて実感してください。